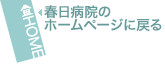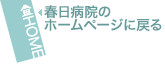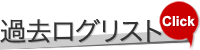|
院内トピックス 雪が降り続いています おまけに猫の作品
2012.02.29(水)
本日は雪が降り続いております。
朝からの雪だったので路面には雪が残っているので車はいつもより慎重に走っているようでした。3月で雪も終わりだと思っている矢先にこの雪でした。
先週末から雪かきでしたが、水分の多い雪になっているので春に近づいてきてはいるのかなと感じられました。水分が多い雪かきは腕がパンパンになります。午後にも再度雪かきをしたいと思います。


余談ですが、老健施設入口に利用者さんが作成した猫の作品がありました。2月22日は「猫の日」でした。「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」の語呂合せだそうです。11月1日が「犬の日」です。語呂合わせで楽しく過ごせそうですね。

ワンポイントメディカル 冷え性対策
2012.02.28(火)
冷え性が起こる原因
「冷え性」は、血行不良によっておこります。血液がうまく流れず、毛細血管にまで流れにくくなる状態が続くことで、血行が悪くなり「冷え」を起こします。また、外気の影響などにより毛細血管が縮むことで血行が悪くなり、特に末端となる手や足の先に影響が出ます。
冷え性からくる病気に注意しよう!!
低体温
最近では低体温の人が非常に多く、健康体でいられる36.5℃以上37℃以下の人が少なくなっています。
冷え性の人は熱を出しやすい筋肉の量が少ない事が多いようです。
特に人のからだの中で筋肉量が多いのはふとももなどの下半身部分で、歩くという基本的な動作が少ないと筋肉量が減少してしまいます。
低体温は、ガンや様々な病気の原因となりやすい体となるため注意が必要です。
 体を冷やす原因 体を冷やす原因
夏は自宅やデパートなど様々な場所でクーラーが効いています。また、ビールやアイスクリームなど体を冷やすものも季節感なく食べます。すると、体の中から冷やして冷たい室内で過ごしていると更に体温を低下させてしまいます。また、ストレスは自律神経の働きが乱れて体温調節機能が失われてしまい体を冷やしてしまいます。
冷え性改善のプチケア
1.足湯
バケツや洗面器などに足首が隠れるくらいまで40℃〜42℃くらいのお湯をはり、10分程度つかって血行促進させます。
2.ホッカイロ
体を温めるためには、大きな血管が通っている部分や体の中心部分をホッカイロで温めるのも効果的です。また、ホッカイロは時間の無いときや外出をしながら体を温めることが出来ます。このとき、ホッカイロが直接肌に触れて火傷をしないように注意しましょう。
3.生姜湯
生姜には、新陳代謝を活発にしたり、自律神経を正常にする成分があります。
生姜湯を飲むと体が温まるのは、生姜の辛味の主成分であるジンゲロールに、強い殺菌力のほか、血行促進の作用があり体を温め冷え症を改善する効果があるといわれています。
4.半身浴
一日の疲れを癒してくれるお風呂。このとき冷え性を改善するのに良いのが「半身浴」です。体が冷えている時に熱いお湯に入ってしまいがちですが、熱いお湯だと温度差によって心臓への負担も大きく、体の芯までは温まりません。38℃〜40℃ぐらいの温めのお湯に下半身をつけて20分〜30分程度ゆっくりと温めることで、血液の流れがよくなり全身を温めてくれます。
冷え性改善には?
冷え性を改善するには、血流を良くすることが大切です。一番効果的なのは筋肉を動かすことです。ジムに通って本格的に運動するだけでなく、普段の生活の中で階段を使う、歩ける距離は乗り物を使わないなどのちょっとした運動や、温めのお風呂に半身浴するなども効果的です。また、自己流食事ダイエットや冷たい食べのもの摂り過ぎは食生活の見直しが必要となります。
日頃からの運動とビタミンや鉄分といった栄養素を意識して普段の食事に取り入れて、冷えの体質改善を行いましょう。
 <記事提供> <記事提供>
社会福祉法人 南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター
http://www.kaigo-hiwada.com/
セーフティチャレンジ特別賞抽選結果が発表されました
2012.02.24(金)
2011年に参加したセーフティチャレンジのお話しになりますが、福島県交通安全協会のホームページを見ましたら特別賞抽選結果が発表されていました。
予備抽選当選1,200チームのうち無事故・無違反が確認された、1161チームの中からベストドライバー賞3本を含む特別賞373本の抽選を行ったようです。多くの参加チームがありました。
当施設でも約30チーム参加しておりますので、これから当選したのか確認したいと思います。来年度も安全運転の為セーフティチャレンジに参加したいと思います。
 参加されたみなさんは当選されたでしょうか。 参加されたみなさんは当選されたでしょうか。
福島県交通安全協会のホームページ
http://www18.ocn.ne.jp/~fkkankyo/p047.html
セーフティチャレンジは、3人1組でチームを結成し、ドライバーがお互いに注意し合い、励ましながら、期間内の無事故・無違反を目指すものです。
住宅改修費支給制度について書
2012.02.24(金)
ご自宅で生活されている要介護、要支援認定を受けている方が、トイレや浴室、玄関などに手すりの取り付け等をご希望の際は、心身状態や住宅環境から各市町村に改修が必要と認められた場合に限り、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給を受けることができます。
改修にあたっては、施行前にあらかじめ支給申請書を各市町村の長寿福祉課等の窓口に提出し、許可を頂いた後、工事後の領収書等の書類の提出が必要となってきます。
また、支給対象となる工事の内容には制限があるので確認が必要です。
支給額について
支給額は上限が定められており同一住宅に対し20万円を限度として自己負担1割で工事を行うことができます。なお転居した場合には改めて上限に達するまでの住宅改修費の支給を受けることができます。
要介護状態が著しく重くなった場合
最初の住宅改修後、認定されている介護度が3段階以上重くなった場合は、例外的に1回のみ支給限度基準額20万円分の住宅改修費支給が受けられます。
支給対象となる改修の種類
1、手すりの取り付け 2、床段差の解消
3、滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の変更
4、洋式便器等への便器の取替え
5、引き戸などへの扉の変更
6、その他1〜5の工事に附随して必要な工事
事前申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書
・住宅改修の予定の状態が確認できる書類
(改修前及び改修後予定の簡単な図や写真)
※「住宅改修が必要な理由書」は基本的に介護支援専門員が作成しますので事前に御相談ください。
事後の申請に必要な書類
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・完成後の状態を確認できる書類
(改修前、改修後の日付入り写真を添付)
・住宅の所有者の承諾書
詳しくは各市町村長寿福祉課等の窓口、地域包括支援センター又はケアマネージャーにお問い合わせください。
<小春日和87号より>
http://www.kasuga-rehabili.com/log/press/97.pdf
南東北病院グループニュース 健康フォーラムin福島2012 〜福島県に元気と健康を〜
2012.02.21(火)
総合南東北病院 創立30周年記念として、「健康フォーラムin福島2012 〜福島県に元気と健康を〜」がたくさんのお問い合わせ・応募をいただいておりますので、お早めにお申し込みください。
総合南東北病院 創立30周年記念
健康フォーラムin福島2012 〜福島県に元気と健康を〜
開催日時:平成24年3月9日(金) 17:00〜
開催場所:ホテルハマツ[郡山市]
福島県郡山市虎丸町3番18号
お申込み:郵便はがき、FAX、インターネット(総合南東北病院ホームページ)より
お申込みフォームはこちら↓
https://secure.minamitohoku.or.jp/minamitouhoku/form/forum/
問い合せ先
〒963-8563 郡山市八山田七丁目115番地
財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
広報課
電 話 024-934-5708
F A X 024-934-5527
主催:財団法人脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院
共催:福島民報社・福島民友新聞社・福島中央テレビ
講演内容
主催者あいさつ:渡邉一夫
財団法人神経疾患研究所付属 総合南東北病院 理事長・総長

講演1:中村仁信(大阪大学名誉教授、彩都友紘会病院長)
テーマ:慢性低線量被曝の人体への影響

講演2:山口和之(衆議院議員)
(東日本大震災復興特別委員会委員 厚生労働委員会委員)
テーマ:2030年のフクシマから今を考える

講演3:福島孝徳
(デューク大学脳神経外科教授、カロライナ神経科学研究所 頭蓋底センター長)
テーマ:21世紀の脳神経外科手術
※「健康フォーラムin福島2012 〜福島県に元気と健康を〜」に関するお問い合わせは、総合南東北病院 広報課へお問い合わせください。
お問合せ先
財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
広報課
〒963-8563 郡山市八山田七丁目115番地
電 話 024-934-5708
F A X 024-934-5527
老健ユニット入口での作品紹介!! 2月号
2012.02.18(土)
老健ユニット入口で季節の作品が展示してありますので紹介いたします。利用者さんで頑張って作った作品です。季節ごとにユニット入口を華やかにしています。
 
・左にダルマはお正月の名残でしょうか。鬼は節分、ハートはバレンタインをイメージして作成しました。赤鬼は怖い顔。青鬼は優しい鬼になっています。
 
・こちらの作品は2月の「行事の日」にちなんだ作品です。左は2月23日「富士山の日」。右は2月2日「バスガールの日」でバスの作品です。バスガールの日は「1920(大正9)年、日本初のバスガールが登場したのがこの日(2/2)です。」
 
・こちらは上記ユニットと別ユニットの作品です。鬼が凛々しく感じます。
3月はどのような作品が出来るのでしょうか。3月はひな祭り、ホワイトデー、イースター等があります。みなさんはどのような行事を思い出しますか。
医療法人社団 三成会
介護老人保健施設 春日リハビリテーション・ケアセンター
南東北病院グループニュース 総合南東北福祉センター市民公開講座のお知らせ
2012.02.16(木)
南東北病院グループニュース
第23回 総合南東北福祉センター市民公開講座
〜いつまでも地域の中で暮らせるために〜
南東北病院グループの総合南東北福祉センターは第23回市民公開講座を下記の日程で開催いたします。
今回は、総合南東北病院 神経疾患研究所 所長 片山宗一先生が「認知症について」と題して講演します。
入場無料となっております。また、骨密度測定などの無料健康チェックコーナーもありますので、多くの皆さんのご来場をお待ちしております。
日時:平成24年3月7日(水) 午後2時〜午後3時
演題:認知症について
講師:財団法人 脳神経疾患研究所
附属総合南東北病院
神経疾患研究所
所長 片山 宗一先生
会場:総合南東北福祉センター 交流ホール
総合南東北福祉センター市民公開講座チラシ
総合南東北福祉センターホームページはこちらhttp://www.kaigo-hiwada.com/
第23回市民公開講座案内ページはこちらhttp://www.kaigo-hiwada.com/blog/002160.html
お問い合わせ・申し込み先(主催)
社会福祉法人 南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター
TEL:024−968−1010(代)
住所:福島県郡山市日和田町梅沢字丹波山3−2
担当:甫喜山(ほきやま)
小春日和 インフルエンザに注意しましょう
2012.02.15(水)
2月に入りインフルエンザが流行しております。体調管理、気にかけていますか?ここでインフルエンザについて再度確認をして、早めの対応をとれるように心がけましょう。
まず、インフルエンザとかぜ(普通感冒)の違いについてです。
○インフルエンザ
急な発熱(38℃以上)、悪寒、頭痛、咳、のどの痛み、鼻水、倦怠感、筋肉痛や関節痛などの全身症状が強い ・・・これらの激しい症状が数日間続く
潜伏期間…24時間〜2日ほど、長くて4・5日後程度
○かぜ(普通感冒)
微熱、悪寒、のどの痛み、鼻水など軽い症状、ゆっくり発症する
・インフルエンザで症状が重くなりやすい方
高齢の方、子ども、妊婦さん、呼吸器疾患・心疾患・糖尿病等の持病のある方
は注意が必要です
次に、ワクチン接種についてです。2009年大流行した「新型インフルエンザ(A/H1N1)」は2011年4月1日より通常の季節性インフルエンザに変わりました。そして、今年のインフルエンザワクチンには、「新型インフルエンザ」と呼ばれた「ブタインフルエンザ(A/H1N1)」も組み込まれており、昨年同様1種類のワクチン接種で済みます。予防接種に優先順位はなく、どなたでも各病院や医院の予約状況に合わせて接種をすることができます。
○ワクチン接種時期
インフルエンザワクチンは接種してから効果が出るまでに、2週間ほどかかります。流行のピークになる前、遅くても11月中旬頃までには接種を終えておくとよいでしょう。
前述した、症状が重くなりやすい方・持病のある方は、早めに主治医と相談しておきましょう。
ちなみに、ワクチンの効果は3〜6ヶ月ほどで徐々に減少していきます。ですので、毎年接種することが必要です。
○ワクチン接種回数
6ヶ月〜13歳未満・・・2回
13歳以上・・・・・・・1回(受験生は2回接種もできます)
※ 接種間隔・・・1回目と2回目の間隔は、1〜4週間程度が目安
○ワクチンの副作用
・接種局所の反応で、発赤・腫脹・疼痛が生じることがある
・まれに、発熱・頭痛・悪寒・倦怠感も起こる
・卵アレルギーの方は、発疹・口唇のしびれ・アナフィラキシーショックなどが現れる可能性がある・・・卵アレルギーの方は主治医に相談して接種を検討しましょう
予防接種も重要ですが、毎日の予防行動を心がけることも大切です。日常生活でできる予防方法を確認しましょう。
 ○日常生活でできる予防方法 ○日常生活でできる予防方法
1.栄養と休養を十分取る
2.流行期には人混みを避ける
3.適度な温度、湿度を保つ
4.外出後の手洗い、うがいの励行
5.マスクを着用する
インフルエンザとワクチン接種について、再確認できたでしょうか。インフルエンザのシーズンになっても、「私は流行に乗らないぞ!」と普段から予防を心がけ生活し、この時期を乗り越えていきましょう。
小春日和84号より
http://www.kasuga-rehabili.com/log/press/94.pdf
出前講座 「転倒予防について」開催しました 鏡石町 さかい集会所
2012.02.15(水)
2月13日、『健康な身体づくりに向けて〜転倒予防について〜』をテーマに、鏡石町内の老人クラブ「さかい寿会」さんへ約1時間、講演や転倒予防体操などを行いました。
講演では、どんな人が転びやすいのかを、理学療法士の視点から分かりやすく解説し、ご自身の転倒危険度をチェックして見直す時間がありました。参加されたほとんどの方が、転倒注意の該当に当てはまっていたご様子で、半ば笑い声も飛び交っておりました。
また、ご自宅でも実践できる体操として、筋肉の柔軟性を高めるストレッチや、筋力トレーニング、さらにバランス能力を鍛える訓練など「転ばないからだづくり」を目的とした実演も披露され、一緒に身体を動かしました。
参加された方からは「すべての動きが役立つと思うし、必要だと感じました。今日少し動かしただけなのに、何だか身体がすごく軽くなったので、これからも続けていきたいです。」など、とても意欲的なご感想をいただきました。


医療法人社団 三成会
南東北春日リハビリテーション病院
健康教室「医学用語について」を開催しました
2012.02.14(火)
毎月当院で開催しています健康教室が2月9日(木)に行われました。今回の講師は樋口健弥先生(総合南東北病院)で、健康教室に参加されているみなさんにはおなじみの先生になっているかと思われます。
今回のテーマは「医学用語について」で、医学用語は数多くあり、また医療従事者でなければ理解できない用語が多いのではないでしょうか。
講演のなかで、認知率の低い用語、理解率の差が多い用語を説明したのちに、よく使われている医学用語を一つ一つ丁寧に、そしてユーモアを加えて説明をし、参加者さんからは「なるほど」「理解できた」との声が聞こえました。最後に先生は、肥満体質の予防と改善も訴え、車に例えて、「(肥満の人は)軽乗用車の排気量でダンプカーを運転しているようなもの。『心臓がとてもとてもつらい』と苦しんでいますよ」と、わかりやすい表現で健康管理を説いて健康教室が終わりました。
また、講演前後に行われている健康チェック(血管年齢・骨密度・血圧・体脂肪の測定)も好評で毎回楽しみにしている方も多くみられました。
 次回の健康教室は、2月25日(土)午後2時より、テーマ「健康診断を受けましょう」「健康診断結果の見かた」を開催いたします。 次回の健康教室は、2月25日(土)午後2時より、テーマ「健康診断を受けましょう」「健康診断結果の見かた」を開催いたします。
出前講座 「腰痛・肩こりについて」開催しました 須賀川市 西袋公民館
2012.02.10(金)
須賀川市社会福祉協議会主催による「福祉(ふくし)レクリエーション講習会」事業として、須賀川市内にお住まいの方を対象に、2月3日に「腰痛と肩こりについて」の演題で出前講座を開催しました。
お話のポイントとして挙げられたのが、次の2点です。
1、腰痛・肩こりは正しい知識を持つ事
2、腰や肩に負担をかけない日常生活を送るよう努力する事
1では、腰痛症の原因や、肩の病気についての解説を、2では、実際にどのような動きが負担が掛からないものなのかを実践で行って、ご来場の方と一緒に体を動かして体験しました。おわりに、「慢性化した場合では、体の問題だけではなく、ストレスへの配慮も欠かさないよう気をつけて下さい」とアドバイスもあり、日常からの心がけと継続性が重要だと分かりました。
写真を見てもお分かりのように、皆さん楽しそうに聞いていらっしゃいますね。


出前講座「寝たきり予防体操について」を開催しました 浅川町 太田輪集会所
2012.02.09(木)
昨年の2月に同地区で開催した出前講座ですが、「腰痛予防体操」の演題で、大変なご盛況をいただきまして、今回も当院職員の中村氏による講演を1年ぶりに開催致しました。
テーマは「寝たきり予防体操」についての講演でした。寝たきり状態で発症することが多い廃用症候群についての解説や、寝たきりにならないために普段の生活でどのような事を心掛けたら良いのか、また、どのような運動・体操をすればより効果的なのかを一緒に体を動かして体験していました。
講話の中で、老後についての教えで、皆さんもご存知の「きんさんぎんさん」のエピソードなども取り込まれ、笑い声が多いに飛び交い、楽しいレクリエーション講習となったようです。来年の出前講座の予約までしていただけるくら好評でした。来年もみなさんの笑顔と健康のために出前講座にお伺いします。
 南東北春日リハビリテーション病院 南東北春日リハビリテーション病院
事務
2月9日(木) 健康教室「医学用語について」を開催いたします
2012.02.08(水)
2月9日(木)午後3時より、当院5階にて健康教室「医学用語について」を開催いたします。
講師は総合南東北病院の樋口健弥先生です。先生の話はとてもわかりやすく、ユーモアたっぷりで、参加者さんから好評です。毎回健康チェックも行っており、予約もありませんので気軽に参加してください。
【市民健康教室】
○ 日 時 平成24年2月9日(木)午後3時〜
○ テーマ 「医学用語について」
○ 講 師 樋口 健弥 先生
○ 場 所 南東北春日リハビリテーション病院 5階会議室
○ その他 健康チェック(骨密度、血管年齢、血圧、体脂肪測定)
※テーマが変更になる場合があります。ご了承ください。
年間健康教室予定はこちらをご覧ください
http://www.kasuga-rehabili.com/blog-files/health23.pdf
ワンポイントメディアカル 気胸 【胸痛がする・呼吸がしにくく、咳がでる】
2012.02.02(木)
ワンポイントメディアカル 気胸 【胸痛がする・呼吸がしにくく、咳がでる】
 気胸とは肺から空気がもれて、胸腔にたまっている状態をいいます。 気胸とは肺から空気がもれて、胸腔にたまっている状態をいいます。
肋骨があるため、胸は風船のように外側に膨らむことができず、肺が空気に押されて小さくなってしまいます。
■症状
 呼吸をしても大きく息を吸えない、激しい運動をすると呼吸ができなくなるなどの呼吸困難、酸素飽和度の低下、頻脈、動悸、咳などがみられます。 呼吸をしても大きく息を吸えない、激しい運動をすると呼吸ができなくなるなどの呼吸困難、酸素飽和度の低下、頻脈、動悸、咳などがみられます。
発症初期は肩・鎖骨辺りの違和感、胸痛や背中への鈍痛がある場合があります。痛みは人によって様々で、全く感じない人もいれば軽度の気胸で激痛を感じる人もいます。
■自然気胸
 理由もなく穴が開いてしまった場合は自然気胸と呼びます。10歳代後半〜30歳代のやせ気味で胸の薄い男性に多く起こります。多くはすぐに穴が閉じられ、漏れた空気は血液に溶け込んで次第に消失します。 理由もなく穴が開いてしまった場合は自然気胸と呼びます。10歳代後半〜30歳代のやせ気味で胸の薄い男性に多く起こります。多くはすぐに穴が閉じられ、漏れた空気は血液に溶け込んで次第に消失します。
緊急性がない場合の初期段階では安静にするのみで自然治癒を待ちます。無理な姿勢・運動、無理な呼吸をしないようにします。
■続発性自然気胸
 肺気腫や肺がんのように何か肺の疾患があり、これが原因となって起こる場合は続発性自然気胸と呼ばれます。比較的、高齢者に多く起こります。 肺気腫や肺がんのように何か肺の疾患があり、これが原因となって起こる場合は続発性自然気胸と呼ばれます。比較的、高齢者に多く起こります。
■緊張性気胸
 胸腔に漏れ出した空気が、反対側の肺や心臓を圧迫している状態を緊張性気胸と呼びます。生命に危険のある状態で、血圧低下、ショック状態となり、緊急に胸腔穿刺の処置を行わなければいけません。緊張性気胸による呼吸困難に対し、人工呼吸は禁忌です。胸腔内圧を更に上げてしまうことになり、肺の虚脱がすすみます。 胸腔に漏れ出した空気が、反対側の肺や心臓を圧迫している状態を緊張性気胸と呼びます。生命に危険のある状態で、血圧低下、ショック状態となり、緊急に胸腔穿刺の処置を行わなければいけません。緊張性気胸による呼吸困難に対し、人工呼吸は禁忌です。胸腔内圧を更に上げてしまうことになり、肺の虚脱がすすみます。
予後について
自然気胸で自然治癒した後も、再発を繰り返す場合や反対側にも起こる場合があります。人によって違いは様々ですが、もともと肺疾患などがある場合はさらに難治性となります。治療後も暫くは安静が必要です。気道内に大きな圧力がかかる、飛行機への搭乗(自動車・バスでも峠越えなど)や、スキューバダイビングなどは事前に医師へ相談してください。喫煙も厳禁です。
<記事提供>
社会福祉法人 南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター
http://www.kaigo-hiwada.com/
|