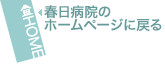

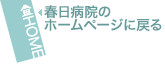 |
 |
|
認知症高齢者の性格・人格の変化とその接し方
2019.12.08(日)
認知症は、脳や身体の疾患を原因として、記憶力・判断力・人とのコミュニケーションなどに障害が起こり、日常生活に支障をきたす状態をいいます。 その症状は記憶障害など主な中核症状から、それに付随する徘徊や多動、暴力暴言など様々で、その中の一つに、性格や人格の変化があることが分かっています。 認知症の方の性格の変化の例と、その接し方についてまとめてみました。
●悲観的なことばかり言う●
高齢者の中には「死にたい」という言葉をよく口にする人がいます。
身体機能が低下し、何をするにも家族や周りの人に手助けが必要になった時、そんな気持ちになるのは無理はないものです。そんな時には、状態にもよりますが、認知症専門のデイサービス等が役に立つ場合もあります。しかしうつ病の場合もあり対応の仕方が異なりますので、専門の医師に相談すべきでしょう。
● 何を勧めても、無気力●
自分の体が思うように動かなくなった高齢者にとって何をするのも嫌がったり、億劫がるのは無理のない事ですが、何を勧めてもしようとしないのが億劫だからとは限りません。
認知症の疾患で脳の一部の損傷により内容が理解できていない場合が多々あり、無気力になる場合があります。その高齢者によくわかる説明の仕方を工夫したり、出来ないところを見極めさりげなく一緒に行動しましょう。又、本人が以前のようにうまくは出来なくなっていることを見られることが恥ずかしいなどの自尊心から行動に移せない場合もあることを理解しましょう。
● 能面のように表情がなくなる●
認知症の病状の一つでもあり、症状が進むと物事の理解力や感受性が鈍くなります。
その結果、症状がなくなり能面のような顔になってしまう事があります。そのような場合はこちらから積極的に話しかけたり、デイサービスを利用したりして、より感動を得られる状況を作りましょう。また、抑うつ状態と思われる時には専門の医師に相談しましょう。
● 気分のむらが激しくなる●
認知症が進むと知的な部分や抑制力の衰えから、気分のむらが激しくなる症状が出る人がいます。
そのような時は焦らず、本人の気分を変える事が第一です。日頃から何か一つは気に入ったものや興味を引く事を介護者は見つけて置き、感情が激しくなった時などにそれを出すのもよいでしょう。また、スキンシップなど人とのふれあいが大切です。
● 子供や赤ちゃんを見ると穏やかになる●
認知症の症状でご本人の記憶が若い時代に戻る場合があります。
その時はご本人が子育ての時代に戻って赤ちゃんを見て穏やかになられているので、介護者側もその当時のお話に共感して穏やかな時間を持つことが安心につながります。 ●性格がきつくなることも●
脳の中のバランスを保とうとする部分に偏りができ、優しい性格と強い性格のバランスが取れなくなるため、偏りができます。
●人柄や性格の変化を感じたら●
認知症のいくつかの型や統合失調症など、人格障害をきたす病気もありますが、明らかに人格が変わったと考えられたときは、専門医に相談しましょう。
中でも人格変化が著しい認知症として、ピック病が上げられますが、無理に治そうとしても障害からくる症状なので効果はありません。介護者側が病気の特徴を理解することで、適切なサポートが可能となりますので、専門家とともにケアしていくことをお勧めします。
当院では、認知症の診断・治療を行う「脳の健康外来」の診察を行っています。 毎週木曜日 8:30〜12:00 受付 医師:酒谷薫 診察は予約不要です。まずはご相談ください。 その他の「認知症高齢者への接し方」の記事 キーワード: |
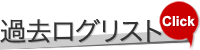
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
|