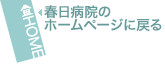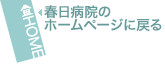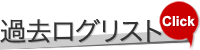|
介護教室 〜入浴介護
2017.05.15(月)
浴槽の種類と工夫
寝たきり、麻痺などの障害を抱える高齢者にとって、入浴は介護者なしで行うことはできません。
しかし、介護者にとっては負担が非常に重く、毎日の介護が腰痛にもつながることもあります。
介護の労力を軽減するためには、まず介護に適した浴槽を選ぶことも大切でありポイントにもなってきます。
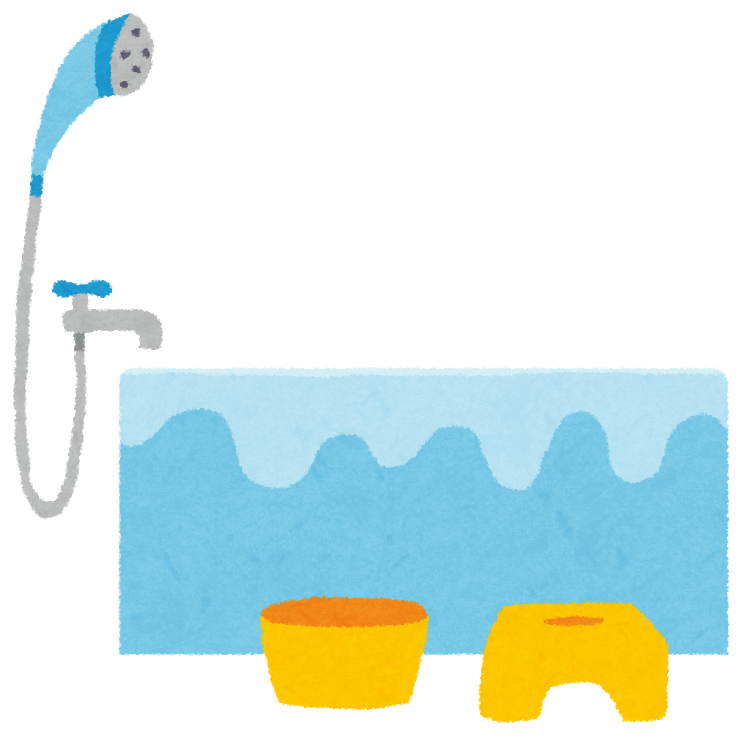
〇洋式の浴槽、埋め込み式浴槽
浴槽が浅いため、下肢に運動障害があってもまたぎやすい。
また下肢をゆったり伸ばすことができる。
〇ポータブル式浴槽
家庭向けである。浴槽の持ち運びができ、自由に場所移動できる。
〇器械浴槽
寝たままで楽に入浴できる。器械を操作するだけで介護が可能。施設に設置されていることが多く、家庭向きではない。
〇深い浴槽
特に下肢に運動障害のある高齢者にとって、深い浴槽はまたぎにくく、介護者の負担も重くなります。
浴槽を変えられない場合は、浴槽に(バスボード)を渡したり、入浴台、手すりなどを使用したり浴槽の底に踏み台を取り付けるなどの工夫をしましょう。

また、浴室の床や浴槽に滑り止めマットを敷く、壁や浴槽の縁に手すりを取り付けるなどの工夫をして環境整備をすれば、負担が軽くなります。
入浴の際の留意点
〇バイタルサインのチェック
事前に全身の状態を観察し、入浴などの可否を判断して、状態に最も合った方法を選択しましょう。
〇準備
食後すぐや空腹時は避けましょう。湯加減を調節し、居室と脱衣場、浴室の室温を少し高くしておく着替えなど必要なものあらかじめ用意しておく。
〇全身状態の観察
脱衣したときに、普段見えない部分の皮膚の変化などを観察する。
〇入浴中の配慮
入浴介護では、浴槽に入ると浮力がかかり、温められて筋肉の動きがよくなるので手足の運動を無理のない程度にすすめる。
ときどき声掛けのほうも実施しましょう。

〇安全性の配慮
浴室や浴槽に滑り止めゴムマットを敷いたり、手すりをつけるなどの転倒防止ややけどの事故防止に努める。
〇入浴後の援助
風邪などをひかないように、身体の水気を十分に拭き取る。伸びた爪を切る(入浴後は爪が柔らかいため)。十分に水分補給を行い、湯冷めしないように休養させる。疲労感や身体状態の変化がないか十分に状態観察をしましょう。
全身清拭
清拭は、高齢者が身体の負担になるため医師から入浴の許可が得られない場合や、設備不足などの場合に行われます。
入浴できても、その回数が制限させられる場合は、必要に応じて清拭を行えます。
汚れやすい陰部、足などは汚れたらその都度こまめに清拭を行います。

<清拭の適切な方法>
 2枚のタオルケットを用意し、1枚は身体の下に敷き、1枚は身体にかける。次に寝衣を脱がせる。 2枚のタオルケットを用意し、1枚は身体の下に敷き、1枚は身体にかける。次に寝衣を脱がせる。
 タオルを熱めのお湯につけてしぼり、顔や耳を拭く。 タオルを熱めのお湯につけてしぼり、顔や耳を拭く。
 そのほかの部分は、石鹸、清拭剤をタオルにつけ、清拭を行う。石鹸や清拭剤は、皮脂を除去しすぎない保護機能のある成分のものを使用する。脱脂作用があり、皮膚を乾燥させるアルコールは高齢者には向いていません。 そのほかの部分は、石鹸、清拭剤をタオルにつけ、清拭を行う。石鹸や清拭剤は、皮脂を除去しすぎない保護機能のある成分のものを使用する。脱脂作用があり、皮膚を乾燥させるアルコールは高齢者には向いていません。
 皮膚のひだの中、麻痺や拘縮、変形のある曲がった四肢や関節の部分は、汚れに気づきにくいので特に丁寧に拭く。 皮膚のひだの中、麻痺や拘縮、変形のある曲がった四肢や関節の部分は、汚れに気づきにくいので特に丁寧に拭く。
 湯にひたした別のタオルで、石鹸分を拭き取り、皮膚炎や褥瘡などがないかよく観察する。 湯にひたした別のタオルで、石鹸分を拭き取り、皮膚炎や褥瘡などがないかよく観察する。
 背部、臀部、足部など、褥瘡のできやすい部分は、手のひらにパウダーやローションをつけマッサージを行う。 背部、臀部、足部など、褥瘡のできやすい部分は、手のひらにパウダーやローションをつけマッサージを行う。
 清拭後には、乳液、クリームなどを塗り、皮膚に潤いを与える。 清拭後には、乳液、クリームなどを塗り、皮膚に潤いを与える。
キーワード:介護,浴槽,風呂介助,浴槽の種類
|